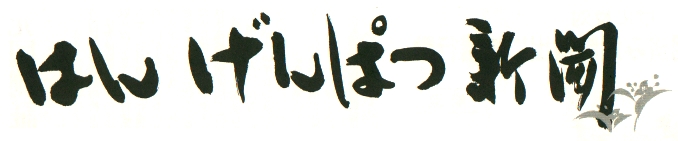編集長の独断偏見録③
「トリチウム等汚染水」をめぐる言説 pick up
東京電力福島第一原発事故で生じた「トリチウム等汚染水」の環境放出については、『はんげんぱつ新聞』2018年10月号で脱原発福島ネットワークの佐藤和良〔敬称略、以下同様〕が報告しているように、経済産業省汚染水処理対策委員会の「多核種除去設備処理水の取扱いに関する小委員会」が2018年8月末に開催した説明・公聴会で圧倒的多数の反対意見が表明された。
それに先立つ6月6日に原子力市民委員会は、以下の提言を含む声明を発表している。「国家石油備蓄基地で使用している10 万トン級の大型タンクを10 基建設して、その中に123 年間保管すれば、トリチウムの半減期は12.3 年であるから、タンク内のトリチウム総量は現在の1/1,000 に確実に減衰する」。
また、海洋放出の非現実性に関しては原子力資料情報室の伴英幸が『ビッグイシュー』2018年10月1日号で、こう書いていた。「東電が定めた目標値はトリチウム1リットルあたり1500ベクレル。これは複数の放射能がある場合に法令が求めている条件をもとにして定めたものである。汚染水をこの条件以下に希釈し、1日あたりの放出量上限を500㎥とすると、すべての汚染水の放出にはなんと500年以上かかることになる」。
2018年10月1日に開かれた前出小委員会では長期保管についても検討するとされたものの、トリチウム以外の核種で基準を超えた処理水をもう一度、多核種除去設備に送って“再浄化”する案のほうが有力視されているらしい。それでは、そもそもの問題は何ら解決しない。
問題の本質
問題の本質は、佐藤が『はんげんぱつ新聞』でも述べていることだが、具体的な状況についてより詳細に記された『DAYS JAPAN』2018年11月号から引用しよう。
「タンクに保管されたトリチウム等を含んだ汚染水(貯蔵液体放射性廃棄物)は、福島第一原発の事故に原因があり、東京電力は発生者責任の原則のもと、厳重に管理し処理しなければならない。また国・原子力規制委員会は、福島第一原発を特定原子力施設に指定しており、タンクの汚染水を適切な方法により安全管理する義務がある。国・東京電力の両者には、高度な注意義務が求められており、海洋放出などの二次汚染による被曝や、人的社会的被害を引き起こしてはならないのだ」。
こうした佐藤の指摘とかけ離れたところに、東京電力の意識はある。前出の小委員会で「汚染水については国民の関心事」という委員の発言に答えて、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの松本純一廃炉推進室長は言う。「認識に差があり、国民の皆様の関心事を十分に理解できていなかったのだと思っている。発電所に目が行きがちで、敷地境界の線量を守ることにとらわれていた。もっと、関心を持つべきだったと反省している」(議事要旨より)。
規制委の傲慢、東電の無責任
2018年5月30日の原子力規制委員会臨時会議からは、タンクはじゃまだから内容物を捨てて解体したいという同委員会の身勝手な傲慢さと、東京電力の無責任さが如実に示された。
原子力規制委員会の更田豊志委員長は言う。「本来であれば、もっとほかのところに使えるはずの用地をタンクが占めてしまっているわけですね。そもそも処理済水のリスクが高いということは私たちは言っていないわけであって、より厳重に管理しなければならないものが今後出てくるわけですね。それの場所も確保しなければいけない。[中略]今後、処理済水よりもっと難しい問題が福島第一原子力発電所の廃炉では生じてくるわけで、ここでこんなことにと言うとふさわしいことばではないけれども、時間を要している場合ではないはずです」。
そして東京電力ホールディングスの小早川智明社長は、「国が責任を持って結論を出すとおっしゃっていただいているので、私どもはそれを信頼して、今、結論を待っているところでございます」と言うばかり。
トリチウムのリスク
トリチウムの危険性については、前掲の『DAYS JAPAN』11月号で英国の海洋汚染の研究者ティム・ディアジョーンズが、次のように述べている(翻訳=渡辺悦司)。
「有機物と結合するというトリチウムの性質は、海岸線沿いや沿岸海域で、有機物の濃度を高めるような条件がある場合にとくに重要となる。つまり、海岸線が侵食されていたり、放射性物質以外でも廃棄物を放出するパイプラインがあったり、河川からの流れ込みがある場合、それらの周辺で海の有機物の濃度が高まる。福島の海岸と海流の下流領域(すなわち福島よりも南の太平洋に面した沿岸)の海域には、このような有機物の流入源が数多く存在するため、よりOBT〔有機結合型トリチウム〕が生成されやすい環境といえるのだ」。
チェルノブイリ救援・中部の河田昌東も同じ号で、トリチウムの健康影響を論じている。同趣旨の『はんげんぱつ新聞』2014年8月号「反原発講座」から引用しよう。「トリチウムが壊れヘリウム原子に変わると、トリチウムと結合していた炭素や酸素、窒素、リン等の原子とトリチウムとの化学結合(共有結合)が切断する。ヘリウムは全ての元素の中で最も安定な元素で他の元素とは結合できないからである。その結果、DNAを構成している炭素や酸素、窒素、リン原子は不安定になり、DNAの化学結合の切断が起こる。このように、トリチウムの効果は崩壊時に出すベータ線の被曝だけではなく、一般的な放射性物質による照射被曝とは異なる次元の、構成元素の崩壊という分子破壊をもたらすのである」。
トリチウム研究の課題
トリチウムの影響研究は、最近では発表される論文が下火になっている印象がある。一時期は潤沢な政府予算が投じられていた核融合研究に伴って、核融合炉で大量に扱われることになるトリチウムについても研究予算がついたということがあるのだろうか。ブームは去った。しかし研究の課題は、多くが未解明のままだ。
『放射線科学』1980年9月号で、当時は科学技術庁に属していた放射線医学総合研究所の新井清彦が、こう指摘していた。「これまでトリチウムは、生物による濃縮が起らないものとされてきたが、他の核種に見られるような、真の意味での濃縮は起こらないとしても、食物として経口摂取されるトリチウム化有機物の種類によっては、体内分布が異なることが判明して来た。これは被曝線量評価に当って、無視できない要因である」。
京都大学原子炉実験所の齋藤眞弘が、31年後の『保健物理』2011年3月号で言うとおり、「環境中でトリチウムの生物濃縮があるかどうかの解明は、古くて新しい課題である」。斎藤は03年1月30日、原子炉実験所の学術講演会で講演し、マウスを使った実験結果を紹介している(『京都大学原子炉実験所学術講演会報文集』、2003年)。
そのひとつは「仔マウスが生まれた直後から離乳まで、母親にトリチウム水を飲ませ続け離乳後の仔マウスの体内に残っているトリチウム量を長時間(40週)追いかけた結果である」。長くなるが、引用を続ける。「離乳後1ヵ月ほどで総トリチウム濃度は脂肪組織を除くすべての組織で投与直後の1‐2%に減るが、残っているトリチウムの量は組織によって大きく異なる。最もトリチウム濃度が高いのは脳であった。このように、量は少ないけれども、長く体内に残るトリチウムがあるということは、水として母親が飲んだトリチウムがどこかで有機結合型のトリチウムに変化することを意味している」。
また、『Isotope News』2011年11月号で茨城大学理学部の立花章は、こう述べていた。「細胞核内で放出されたトリチウムβ線の飛程の末端がDNA分子に重なった場合には、DNAに比較的大きな線量が与えられることになる。DNA分子上で複数の電離が生じると、クラスター損傷と呼ばれる複雑なDNA損傷が形成されることが知られている。クラスター損傷は修復しにくい損傷であるため、生物にとっては重大な影響を及ぼし得る損傷である」。
そのことを含め、多くの課題が残されていることは、『プラズマ核融合学会誌』の2012年2~4月号に連載された「講座 トリチウム生物影響研究の動向」に詳しい。
最後におまけをひとつ。放射線医学総合研究所でプルトニウムの内部被曝影響研究に従事していた松岡理が著書『プルトニウム物語』(テレメディア)で、プルトニウムは危険でないと強調したいがために書いていたことだ。
プルトニウムの利点として「無傷の皮膚からは吸収されません。これは放射線防護上ではたいへん有利なことです。3H〔トリチウム〕は無傷の皮膚からも吸収されます」。
さらにもうひとつ、おまけをつけておく。『原子力資料情報室通信』2018年10月号に載せたものの再録である。
トリチウムのクリアランスレベルが決められるまで
クリアランスは規制解除と訳される。本来は放射性廃棄物としての規制対象だが、あるレベル以下なら規制を解除するというものだ。あるレベルは、年間10マイクロシーベルトと定められた(放射線審議会基本部会、1987年12月)。そこで、核種ごとに年間10マイクロシーベルトの被曝をもたらしうるクリアランスレベルが1グラム当たりのベクレル数として求められる(少なくとも10トン程度の固体ごとに平均された濃度として算出)。
トリチウムについての値は、文献によって1グラム当たり100ベクレル未満から1万ベクレル以上までおそろしく幅広いらしい〔以下、1グラム当たり何ベクレルという表記は略し、数値のみ記載〕。それは、トリチウムそのものの危険性の評価に桁違いの幅があること以上に、どのように被曝するかの経路の条件で大きく違ってくる。
国際原子力機関(IAEA)が1996年1月に出した技術文書「TECDOC‐855」では、文献により1,000~10,000まで幅があるとしたうえで、単一代表値を3,000とした。それを受けて日本では原子力安全委員会の放射性廃棄物安全基準専門部会が「日本における日常生活の態様、社会環境等を基に」独自に検討し、1999年3月、200と決定した。その過程では1998年4月の第24回部会で埋設処分地の井戸水を飲むことで71という数字が出てきたが、再検討の結果、11月の第26回部会では290に変わった。他方、埋設地で収穫された農作物の摂取による被曝が220から170に変わり、これをもとに200と決定されたのである。実は「TECDOC‐855」でも農作物の摂取による被曝が170と計算されたが、保守的過ぎる経路として除外されていたという。
2004年8月になると、IAEAの安全指針「RS‐G‐1.7」が出て、100となった。それまでは成人を対象にしていた基準づくりに1~2歳児も対象とされたからである。原子力安全委員会の放射性廃棄物安全基準専門部会でも1~2歳児を対象に再評価し、同年12月9日、60に変更された(やはり埋設地で収穫された農作物の摂取による被曝)。ただし、有意の差はないことと国際的整合性を理由にIAEA安全基準を適用することは適切と結論。4日後の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会でIAEA安全基準の100とすることが決定される。 原子炉等規制法の改正は2005年5月に成立した。
値が二転三転したのはトリチウムそのものの危険性の評価が大きな理由ではないかもしれない。それでも、仮に海洋投棄されたりすれば、どんな経路でどれだけ被曝するかわからないことは確かだと言えるだろう。クリアランスレベルを決めるために考えられた多数のシナリオに、もちろん海洋投棄はなかった。(西尾漠)