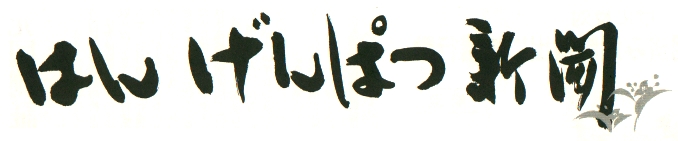鈴木 達治郎(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)
核燃料サイクルと高速増殖炉(FBR)の開発・実用化は、日本が原子力開発に取り組み始めた1956年以来の目標であり、今も日本の原子力政策の重要な柱とされている。しかし、肝心のFBR開発は、原型炉「もんじゅ」が廃止され、その将来は不透明なうえ、1992年に建設を開始した六ケ所再処理施設(青森県六ケ所村)は、事業開始が26回も延期されて、2024年7月現在も稼働をしていない。公式の予定では、本年度上期の操業開始が予定されているが、その見通しは決して明るくない。
世界では、FBRと核燃サイクルの実用化をあきらめ、使用済み燃料を「廃棄物」として処分する「ワンス・スルー(直接処分)」路線が主流となっている。その理由は、第1に経済性・必要性がないこと、第2に回収されるプルトニウムが核兵器の材料となるので、核不拡散上リスクが高いこと、などがあげられる。核燃サイクルは原発を推進する立場であったとしても、その合理性に疑問が投げかけられているのである。
ではなぜ日本は核燃料サイクル路線をあきらめないのか。その構造的問題は何か。果たして出口は見えるのか。
核燃サイクル継続の構造的問題
まず、六ケ所再処理施設のような大規模プロジェクトは、変更・中止が極めて難しい。大規模でかつ長期の投資に伴う契約や債務保証問題など、キャンセルすることの損失があまりにも大きい。国家管理事業となった今、その決定権は政府に移ったことになるが、政府が政策変更することにより大きな負債を抱えてしまうことになる恐れがある限り、変更するインセンティブは働かない。青森県も、長期にわたる交付金の継続や雇用を考えれば、当事者として変更を要請する理由はない。日本原燃には9電力会社以外に、日本の主要原子力企業が出資しており、彼らも同様にキャンセルする理由は見当たらない。
このように、核燃サイクルを推進してきた、政府(経産省)、電力会社、青森県、原子力企業にとって、六ケ所再処理施設を維持する方が得策であることは明らかである。
また、法制度も全量再処理政策と整合性を取るべく、整備されてきている。最も顕著な例が、特定放射性廃棄物の最終処分法で、地層処分の対象となる放射性廃棄物に使用済み燃料が含まれていない。再処理後の廃棄物のみが対象となっている。日本では、使用済み燃料の直接処分が法制度のうえでは不可能ということだ。また、再処理等拠出金法では、毎年発生するすべての使用済み燃料の将来の再処理費用をあらかじめ、電力会社が拠出することを義務付けられている。全量再処理費用の前払いを法律で義務付けられていることになる。もちろん、そのツケは消費者である我々に負担がかかる仕組みである。
法制度ではないが、電気事業者・政府と青森県が交わした合意文書に、六ケ所再処理工場が事実上のキャンセルとなれば、使用済み燃料を青森県から搬出するという趣旨が明記されており、これが六ケ所再処理工場をやめられない大きな理由の一つとして挙げられてきた。いわば、止めたくてもやめられない「がんじがらめ」の状況にあるのだ。
出口はあるか
この「がんじがらめ」の状況を打破するにはどうすればよいか。海外で再処理路線から撤退した例を参考に、次の4点を提案したい。①使用済み燃料の中間貯蔵容量の拡大(不要な再処理をやらない) ②高レベル放射性廃棄物処分の対象に使用済み燃料を含める(直接処分を可能にする) ③独立した「第三者機関」による核燃サイクルの検証(合理的判断につなげる) ④撤退した場合のコスト負担の検討と地元対策。これらが必要だ。
(2024年8月号掲載記事)
次の記事 原発の新増設とRABモデル
はんげんぱつ新聞の発行は、みなさまの購読によって支えられています。ぜひ定期購読をお願いします。申し込みはこちら