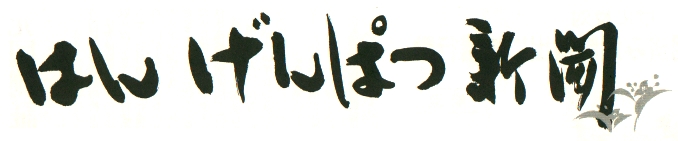湯浅 一郎(環瀬戸内海会議共同代表)
再処理をはじめ核燃料サイクルが破綻しているにもかかわらず、行き場所がない核分裂生成物を新たに生み出す原発の再稼働を本格化させる、あまりに愚かで無責任な政策が続いている。この状況で、核施設が面する海のほとんどは、生物多様性の保全を目的として設定された海洋保護区であることを訴えていくべきことを提起したい。
1992年6月、ブラジル・リオデジャネイロでの国連環境開発会議(地球サミット)において人類は気候変動枠組み条約と生物多様性条約をセットでつくった。以来、30数年間、国際的取り組みを進めたが、両者ともに成果の兆しが見えてこない。2010年、生物多様性条約第10回締約国会議は、2020年までに海の10%を保護区にすることを含む愛知目標に合意した。これを受け、環境省は、2012年、自然公園法、漁業法など既存の法律に基づいて作られている「特定の区域」を、そのまま海洋保護区とする方針を固めた。2020年には、陸・内域20.3%、海域13.3%が保護区となり、愛知目標は達成されたとされ、沿岸域の大部分が海洋保護区となっている。この中で最も大きな面積を占めるのが漁業法に基づく共同漁業権区域である。そして2022年、第15回締約国会議で、2030年までに「陸、海の30%以上を保護区にする」(いわゆる30by30)という高い目標を掲げた昆明モントリオール合意を採択した。 世界の海洋保護区をみることができる国際データベースのサイトで原発立地地点の海洋保護区を調べ、図にして・・・
この記事の続きは、本紙で