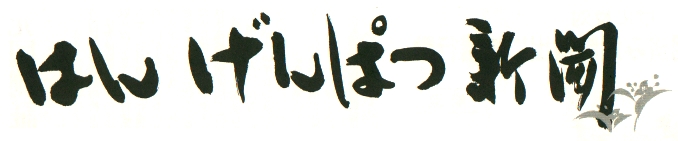桃井 貴子(気候ネットワーク東京事務所長)
現行のエネルギー基本計画(エネ基)における「石炭」の位置づけは、「安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」である。これを根拠に各電力会社は石炭火力を新設し、2020年のパリ協定がスタートした後から現在に至るまでだけ見ても、16基925.7万kWを新たに運転開始した。先進国が次々と「脱石炭」を宣言して既存の石炭火力を減らしている中で、日本の逆行とも言える奇行は国際社会で批判にさらされ続けてきた。今回のエネ基改定の重要な論点は、これを見直し、「脱石炭」を位置付けられるかだ。
石炭に関する国際合意をみると、まず2021年の気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)の最終合意で、はじめて「排出削減対策のとられていない石炭火力発電の削減(フェーズダウン)を加速する」という文言が入った。さらに翌年のG7エルマウサミットでは「排出削減対策がとられていない石炭火力発電を廃止する目標に向けて具体的かつタイムリーにステップを踏む」とし、表現を「廃止(フェーズアウト)」に踏み込んだ。その後の交渉でもこれまでの合意が継承されるとともにさらに昇華し、今年のG7プーリアサミットでは全廃の時期を「2030年代前半、または各国のネット・ゼロの道筋に沿って気温上昇を1.5℃に抑えられるスケジュールで」との年限も定められた。日本はこの交渉で唯一反対の立場をとり続け、合意に後ろ向きな姿勢を示した。日本への配慮から極めてまどろっこしい表現となっているが、この文書を素直に読めば遅くとも2035年までには石炭火力を全廃しなければならないことになる。
問題は「排出削減対策のとられていない石炭火力発電」の定義である。IPCC第六次評価報告書では、「CCSによりCO2を90%程度回収するような対策がとられていないもの」と示されており、米国でも90%削減できていなければ「削減対策のとられた」とはみなさない。
日本には169基の石炭火力があるが(2024年6月末時点・https://beyond-coal.jp/)、90%以上削減ができている石炭火力は1基もないし、今後の見通しもまるでたっていない。一方で、この間日本は、石炭火力を維持し続けるための方策をつくってきた。その主要な策が「アンモニア混焼」である。
政府が力を入れるGXの施策に、水素等燃料の推進がある。水素と窒素を合成したのがアンモニアで、「水素等」に含まれる。石炭火力に混ぜて石炭燃料を減らすことでCO2の削減になるとし、様々な形で支援策を講じている。とはいえ現在、愛知県にあるJERAの碧南火力4号機で20%混焼の実証試験をしている段階で実用化には至っていない。政府は、2030年までの石炭火力への20%アンモニア混焼の導入・普及を目標としているが、それを「削減対策のとられた石炭火力」と位置付けたい思惑が見えてくる。
アンモニア20%混焼では、残りの80%は石炭燃料でありCO2を大量に出し続けるため、IPCCの定義とは全く異なり「対策がとられた」とみなすのはあまりにお粗末だ。さらに問題は、アンモニアの原料が天然ガスなど化石燃料であり、製造時に大量のCO2を出すため、ライフサイクルでみれば、ほとんど削減できていないことだ。製造のインフラも整っておらず、化石燃料を合成するためコストも跳ね上がる。そもそも石炭のメリットとされていた「安定供給性」や「経済性」の観点からも問題で、何のメリットも見出せない。国民の税金や電気代が跳ね上がるばかりだ。これで世界をリードするなどと言って
も、勝ち目はない。既存の電源の温存ではなく、早く石炭から脱却して再エネに切り替えるエネ基にすべきだ。
(2024年7月号掲載記事)
次の記事 出口なき迷走?核燃料サイクル
はんげんぱつ新聞の発行は、みなさまの購読によって支えられています。ぜひ定期購読をお願いします。申し込みはこちら