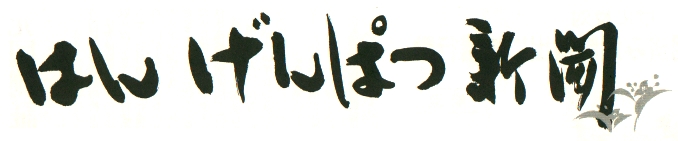大野 隆一郎(柏崎刈羽原発活断層問題研究会代表)
福島原発事故から約12年が経ちますが、未だに溶け落ちた核燃料(デブリ)はそのままで、撤去の見通しさえ立っていません。燃料デブリに地下水などが触れることによって毎日130㌧もの汚染水が増え続けています。
そもそも東京電力は原発の建設に当たって、敷地の地質と地下水の問題を重要視していませんでした。
福島第一原発は海抜35㍍ほどの海岸段丘を掘り下げて、大年寺層という地層の上に原子炉建屋が設置されています。大年寺層は新第三紀末鮮新世の砂岩や泥岩から構成される地層です。東電は固い岩盤であると称していますが、土木工学的には軟岩に分類され、重要構造物の基盤としては大変不安定であると言わざるを得ません。
敷地内には豊富な地下水が流入し、建設時には排水処理で大きな苦労をしたことでしょう。原子炉建屋および重要構造物の周囲には地下水を汲み上げるためのサブドレインという井戸がたくさん配置され、恒常的に水抜きをしています。地下水位が高いため、水を汲み上げないと浮力が生じて建屋が不安定になるからです。
汚染源となるデブリのある建屋に地下水を近づけないために、これまでに多くの対策が講じられてきました。地下水を汲み上げるサブドレインや地下水ドレイン、雨水がしみ込まないように地表を舗装するフェーシング、海側遮水壁、建屋を取り囲む凍土壁(陸側遮水壁)など。しかし、いずれも効果は限定的で、地下水の流入は期待通りに減ってはいないのです。一体何故でしょうか。
東電の資料によると、原発敷地の地質構造は大年寺層の砂岩や泥岩の地層が定規で平行線を引いたように西(陸側)から東(海側)にゆるく傾斜した同斜構造をしています。これはボーリング資料から2点間を機械的に結んで作成した地質構造図で、実態を正確に表していないものと思われます。不正確な地質情報に基づいて対処療法的にいくら地下水対策を講じても、その効果が限定的なものとなることは自明なことです。
東電の資料に疑問を抱いた地学団体研究会の有志が独自の調査活動を行いました。その成果が『福島第一原子力発電所の地質・地下水問題-原発事故後の現状と課題-』と題する論文集として、昨年7月に刊行されました。また、この論文集をわかりやすく要約した地団研ブックレットシリーズ16『福島第一原発の汚染水はなぜ増え続けるのか-地質・地下水からみた汚染水の発生と削減対策-』が刊行されています(いずれも地学団体研究会 Tel03-3983-3378 から入手可)。
上記の研究報告によると福島第一原発の基礎地盤となっている大年寺層の砂岩層(透水層)や泥岩層(難透水層)は大変複雑な形態をなし、地層が厚くなったり薄くなったり、ちぎれたりしています。このように層相変化の激しい地層は乱堆積(スランプ)構造とよばれ、おもに海底地すべりによって生じたものと考えられています。東電資料のように定規で平行線を引いたような地層の重なり方でないことが明らかになったのです。これでは地下水が上下左右、自由に移動できることになり、いくら遮水壁や凍土壁を作っても下から流入できるわけです。
地団研ブックレットでは、①当面の対策として汚染水の発生量を減らし、燃料デブリの取り出しを速やかに進めるためにサブドレインを増強する。②長期的な対策として、大型の水抜き井戸(集水井)を10 ヵ所ほど設置する。③長期的な対策の二つ目として、凍土壁よりも広い範囲で、深い位置までの「広域遮水壁」を設置する。を提案しています。これらの対策はすぐにでも実施でき、より確実に長期にわたって汚染水の発生を抑えることができます。国や東電は地質や地下水をきちんと調査をし、一刻も早く抜本的な対策をとらなければなりません。
はんげんぱつ新聞2023年2月号掲載記事